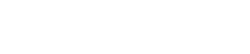本日から三原市久井町和草地区の真言宗千林寺様にて石垣の修復工事に入らせていただきました。
こちらのお寺様には本当に多くのご縁を頂いており、先代ご住職のお墓、既存の宝篋印塔の修復工事、玉垣石の修復工事等に携わらせて頂きました。
本当に感謝しかありません。
今回は画像の下部分の石垣が一部崩れかけている部分がある為そちらの修復となります。また階段の袖石がずれている為そちらも修復をさせて頂きます。
ご住職のお話によると、こちらのお寺が約900年前からあり、画像の石灯篭は約600年前のもの、石垣も数百年前にできた物とのことです。何百年もの間、コンクリートが存在しない時代にいわゆる空積みで作られた石垣が大きな修復もせずいるというだけでも驚きです。
今回の修復箇所は、石垣の上の土地に生えている木を伐採する際に重機が入ったときにその重みやひねりなどの圧力で崩れた箇所が出来たとのことです。

今回はこちらの石垣の上部約50㎝部分のズレが激しい部分を修復します。
現状に近い形での修復という事でセメントを使わない方法をとって行うことになります。
自分としても初めての経験だった為段取りなど勉強になりました。

分かりづらいかもしれませんが、修復する石に番号を書き、一旦崩した後も元通りの石の並びに戻せるようにしておきます。




まずは石垣が外しやすい様に後ろ部分の土を掘り返してから人力で取れるものはとり、大きなものはクレーンを使って取り外していきます。
その後、縦、横の出具合を慎重に調整しながら間に小さな石を詰めつつ固定していきます。排水と強度アップにつなげる為バラスを最後に入れていきます。

6割ほど終えたところで本日は終了です。明日もお伺いさせていただきます。